
ある日の出来事。
夕方から雨が降り雷も鳴ったりして、
雷が鳴るたび子供が「今ピカっとした!」と興奮気味に反応。
大人は気にも留めないけど、子供にとっては一大事だよな・・とか思いつつ
お風呂に入りました。
お風呂から出た後、パンイチ姿で何かコソコソしている。
はいたパンツをハイウェストな感じで持ち上げている。
布団に入った後もしきりにパンツをあげており(今寝る時はパンイチ)
やっと気づきました。
へそ隠そうとしてる・・・!
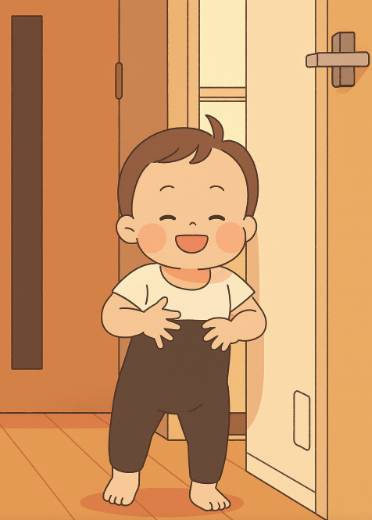
保育園で先生に教わったのかな?
可愛いなぁ・・
雷さまがおへそを取っちゃう?食べちゃう?みたいな
そんなお話もあったなぁとなんか懐かしくなりました。笑
ふと、そもそもどういう話だったっけ?と気になったので調べてみました。
「雷さまにおへそを取られる」ってどんな話?
「雷が鳴ったら、おへそを隠しなさい!」
子どものころそんなことを言われた記憶がうっすらあります。
この言い伝えは調べたところ、諸説ありますが
雷が鳴ると雷さま(雷神)が天から降りてきて、人のおへそを取ってしまう
という昔話から来ています。

絵本や昔ばなし、アニメなどでもよく描かれており
子どもにとってはちょっと怖くて、でもどこかユーモラスな存在として扱われています。
科学的な根拠があるわけではありませんが、
この言い伝えは長い年月を経て受け継がれてきました。
なぜおへそ?言い伝えに込められた意味

「どうしておへそなの?」と聞かれると、少し困ってしまうかもしれません。
おへそは身体の真ん中にあり、命の根っこともいえる場所です。
母親とつながっていたへその緒の名残でもあるため、
「おへそを守る=命を守る」といった象徴的な意味もあったのでしょう。
また、雷という自然の力を「人間にはどうにもならない神さまの怒り」と
とらえていた昔の人々にとって、
「大切な部分を守らなければいけない」という警告として
おへそが象徴的に使われたと考えられます。
ほんとうの理由はシンプル?「体を冷やすな」

実はこの言い伝え、健康を守る知恵としての側面もあります。
雷が鳴るような夏の夕立のあとには、急に気温が下がることがあります。
子どもが服をめくってお腹を出したままだと、体が冷えてお腹を壊してしまうことも。
「雷さまが来るよ」とちょっと怖がらせることで、
自然にお腹を隠させ、体調を崩さないようにしていたのです。
現代で言えば、「お腹冷えるからシャツしまいなさいね!」という注意を
昔の人はもっとユーモラスに、かつ印象深く伝えていたんですね。
他にもある!日本のちょっと不思議な言い伝えたち
日本には他にも子どもを守るためや、
生活の知恵を伝えるためにさまざまな言い伝えが残されています。
たとえば、
- 「夜に爪を切ると、親の死に目に会えない」
→ 夜は照明が暗く、怪我をしやすいからという教訓。 - 「くしゃみを3回したら風邪をひく」
→ 風邪の初期症状を見逃さないように注意を促す言い回し。 - 「しゃっくりが100回出ると死ぬ」
→ 医療が発達していなかった時代に、長引くしゃっくりが病気のサインだったから。
どれも非科学的なようで、実は日常生活の注意を子供に伝わるように伝える手法。
昔の人の知恵とも言えますね。
おとなの伝え方次第で捉え方が変わる。それが子供!

単純に「お腹冷やしちゃダメだよ!」と伝えても、子供は聞いちゃくれません。;
でも雷が鳴ったときに、
「昔はね、雷さまが怒ってるからおへそ隠しなさいって言われたんだよ」
と話せば、子どもは興味津々で耳を傾けてくれます。
そのうえで、「体を冷やさないようにって意味もあるんだよ」と伝えることで、
子供にも伝わり、風邪の予防行動にも繋がりますね。
まとめ

「雷さまにおへそを取られるよ!」という言い伝えは
ただの迷信ではなく、子どもの健康を心配する
昔の人の優しさや知恵が詰まった言葉でもあったんですね。
子供といると、それ知ってるけどどういう意味だっけ?と思うことの連続で
調べてみて新たな発見も多く楽しいです。
これを機に次は雷さまの絵本も借りてみようかなと思いました。
おへそにまつわる昔話が見つかるかも?
ここまで読んでくださりありがとうございました♬


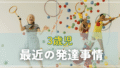
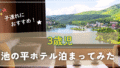
コメント